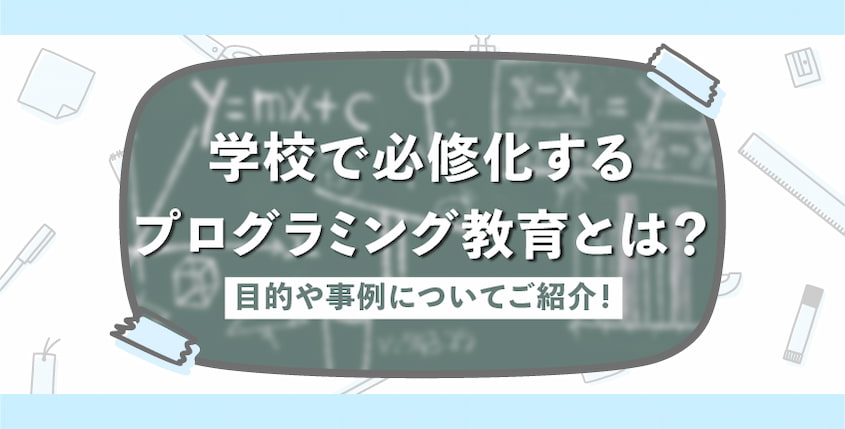
文部科学省が、学校教育法に基づいて編成した「学習指導要領」を改定したことにより、プログラミング教育が必修化されました。
学校指導要領は、全国どこの学校で教育を受けていても、一定の水準を保てるように編成されており、約10年ごとに改定されています。
プログラミング教育は、2020年度から小学校、2021年度から中学校で必修化されていて、2022年度から高等学校で必修化されます。
ここからは、プログラミング教育が、どのような目的により必修化され、学校教育に組み込まれているのか、事例を元に詳しくご紹介していきます。
学校で必修化されるプログラミング教育とは

学校教育で必修化されるプログラミング教育は「時代を超えて普遍的に求められる力」を育成することであって、Webデザインをブラウザで見られるように、ソースコードを記述する「コーディング」を覚えることが目的ではありません。
プログラミング教育の目的は、プログラムを動かすのではなく「問題解決能力等の育成」や「論理的思考力」「創造性」を育むことです。
これらは、普遍的に求められる「資質や能力」を身につけることができるため、情報活用能力を育成するための一つです。
プログラミング教育が必修になる理由
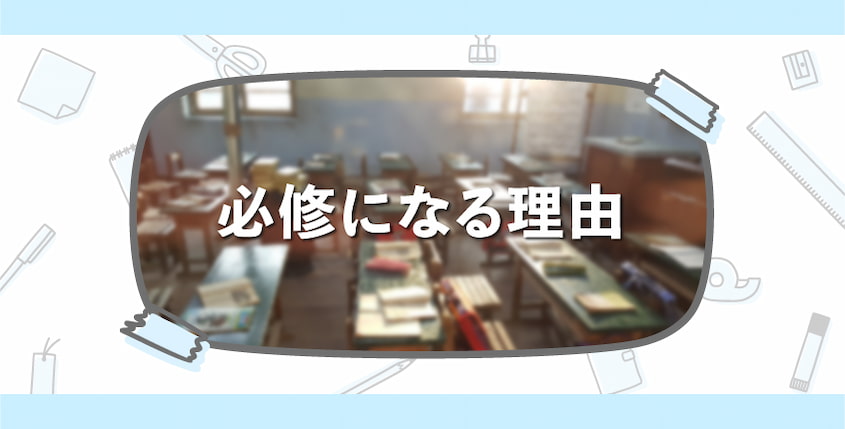
プログラミング教育は、教育現場が「社会の変化」に対してどのように向き合い、対応していくかが重要になります。
ここでは、プログラミング教育がなぜ必要となり、必修化されることになるのか、その理由について解説していきます。
情報化やグローバル化といった社会的変化
人間の予測を超える勢いで、社会全体の情報化やグローバル化が加速し、学校で教えていることが、通用しなくなる時代に突入すると言われています。
また、情報端末の仕組みを理解することにより、主体的な活用に繋がって、効果的に活用することができます。
AI(人工知能)の進化
将来的に、仕事の約半数が技術革新によって自動化され、人工知能(AI)が意思決定する時代になると予測されています。
人間の仕事が自動化されることにより、AIに仕事を奪われるのではないかという不安の声に対して、文部科学省は学習指導要領の改定を行いました。
「変化を前向きに受け止め、主体的に向き合い・関わり合い、自らの可能性を発揮し、より良い社会と幸福な人生の創り手となるための力を子どもたちに育む学校教育の実現を目指す」
引用:小学校プログラミング教育の概要 1 / 文部科学省

プログラミング教育を必修化する目的
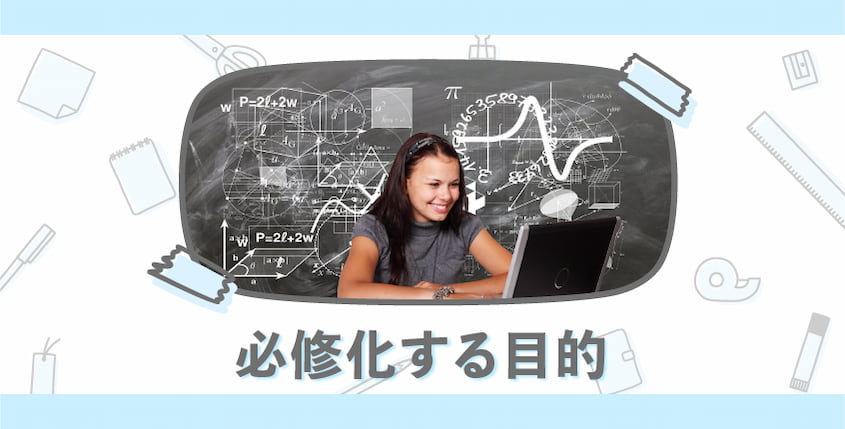
プログラミング教育の本質は、自分で考えて形にしていく「プログラミング的思考力や行動力の育成」です。
そして、これらの最終目的は、社会変化によって発生する「IT業界の人材不足」を補いながらも、将来の選択肢が広がるための役立つスキルにも繋がります。
ここからは、学校教育で「プログラミング教育」を必修化する目的について、詳しくご紹介していきます。
論理的思考を身につける
機械には感情がないので、曖昧な表現を理解したり、気持ちを察することができないため、複数の情報から筋道を立てて、関係性や状況を整理します。
そこで、人間も機械と同様に論理的思考を身につけることにより「プログラミング的に考える力」を身につけることができます。
プログラミング的思考を育む
自分が意図する答えや方向へ進むためには、どのような動きが必要で、どのような順序で取り組むべきなのかを理解して「論理的に考えられる力」を育むことが必要です。
アルゴリズム的な思考になるので、育成すべき能力として「思考力」「判断力」「表現力」が挙げられています。
より良い社会を築く姿勢を育む
身近な問題を解決するために、情報端末を効果的に活用することで「主体的に取り組む姿勢」や「より良い社会を築こうとする姿勢」を育むことができます。
さらに、情報社会は、情報技術によって支えられているのだと、気づくきっかけにもなります。
プログラミング教育の必修化に対する取り組み

プログラミング教育の必修化により、各教育現場では、具体的にどのような取り組みが行われているのでしょうか。
ここからは、プログラミング教育が2020年度に必修化された小学校、2021年度に必修化した中学校、2022年度に必修化される高等学校についてご紹介していきます。
「みらプロ2020」【小学校】
文部科学省・総務省・経済産業省が運営していた「みらプロ2020」は、プログラミング体験を含めた総合的な学習の時間において、約35分間の指導案を用意しました。
協力企業と連携して取り組んだ事例を活用して、プログラミング教育の円滑な指導を支援しています。
参考:プログラミング教育ポータル
D「情報の技術」【中学校】
中学校では、指導に対する入り口と出口を決定し、小学校の指導から高等学校で学ぶ「情報I」までをスムーズに連携することを目指します。
技術・家庭科(技術分野)で、プログラミングの仕組みを科学的に理解する能力を養い、総合的な解決に向けた指導を行います。
参考:中学校技術・家庭科(技術分野)プログラミング教育
「情報I」必修化【高等学校】
高等学校の情報科は「社会と情報」または「情報の科学」の選択必履修から、共通必履修科目として「情報I」を設けることになりました。
情報Iでは、「基本的な情報技術や情報の扱い方」と「コンテンツ作成や発信の基礎になる情報デザイン」について指導します。
情報モラルを身に付けさせ情報社会と人間との関わりについても考えさせる。
引用:高等学校情報科「情報I」教員研修用教材
まとめ
学校教育にプログラミング教育が導入されることで、授業は「暗記型」から「思考型」へと転換することができます。
授業に対する探究心を高め、受動的な学習から能動的な学習を促し、情報社会において端末を効果的に活用できる思考を育みます。
「Welcomist VR」は、学校PR(バーチャルオープンキャンパス)のみならず、生徒が主体的にチャットボットを運用することも可能なため、臨場感溢れる「学び」を提供することも可能です。
当社では、学校でのプログラミング教育をサポートするため、ICTを活用した「教育プログラムの提供」を開始しました。
日出学園中学校・高等学校では、当社の「Welcomist VR」を導入いただき、学校紹介を目的としたPR活動のみならず、プログラミング教育の一環として、バーチャルツアーに組み込んでいるAIチャットボットの運用(質問内容とその回答)を、生徒主体で行っています。
生徒目線だからこそ生まれる「質問と回答」は、学校説明会では聞きにくい受験生の「本音」や、教師目線による型に嵌った質問内容ではないので、受験生にとっても有意義な時間を過ごすツールとして活用できます。
また、シナリオ構築を含む情報技術に触れることで、論理的なプログラミング思考を育むことにも繋がり、AIチャットボットの制作過程で、学校の魅力や特徴について再認識することができます。
【日出学園中学校・高等学校が導入している「Welcomist VR」】
 画像出典:日出学園中学校・高等学校 バーチャル学校紹介
画像出典:日出学園中学校・高等学校 バーチャル学校紹介
関連記事:VRを活用したオープンキャンパスが急増中? 令和のバーチャルキャンパスツアーに迫る!
サービスについての詳しい資料はこちらからダウンロード
随時、トライアルやオンライン商談を行っているので、導入をご検討されている際には、是非、デモンストレーションをお試しください。
実証実験の有無・ご不明点・ご相談ごとについても、オンラインにて受け付けておりますので、下記よりご予約ください。
オンライン予約はこちら

